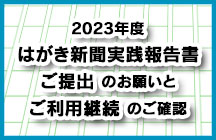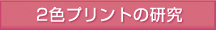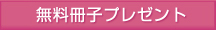読点の打ち方には、十分に注意してほしい。
読点の打ち方には、十分に注意してほしい。
 読点を打つルールには、長い修飾語の境界、逆順のとき、誤解防止の
読点を打つルールには、長い修飾語の境界、逆順のとき、誤解防止の
ため、などがある。
![]()
読点「、」は、センテンスを区切って分解するいちばん有力な方法です。読点のルールに関して悩む読者も多いのではないでしょうか。文章の専門家の間でも、読点のルールには、さまざまな独自のルールが提唱されていて、私たちをいっそう悩ませます。
個人的には、講談社刊『日本語の作文技術』の著者である本多勝一氏が提唱しているルールがいちばん合理的で分かりやすく感じます。本多氏の理論を参考にしながら、私独自の考えも加えた以下の原則を私自身は使っています。
![]()
ここで言う「修飾語」とは、一般的に言われる「形容詞」や「副詞」のような修飾語とは異なるものです。本多氏は、まず、動詞を含んだ「述部」を文の中心的存在、主役と考えます。次に、この述部と「係り受け」の関係で、つながるすべての「句」を脇役の「修飾語」と考えます。次の例文で説明しましょう。
「彼女は、大雨の日ではあったが、弟と一緒にプールへ行った。」
述部が主役ですから、この例文の主役は、「プールへ行った」部分であると考えます。一方、この主役に状況説明を加える脇役の修飾語は以下の【A】から【C】の三つの部分です。
【A】 彼女は(→プールへ行った。)
【B】 大雨の日ではあったが(→プールへ行った。)
【C】 弟と一緒に(→プールへ行った。)
この三つの修飾語の境界に読点を打つので、例文のようになるわけです。
さて原則1は、述部を飾る修飾語が長い場合に限り、修飾語どうしの境界に読点を打つ、というものです。最後に置かれる述部直前の修飾語と述部との境界には、読点は必要ありません。先ほどの例文では、各修飾語がそれほど長くないので、読点を打たなくてもかまいません。
ただし、「修飾語が長い」の定義が、理系の学問のように厳格にあるわけではないので、判断は書き手の主観にゆだねられることになります。そこに書き手の個性が表れるわけです。
![]()
日本語は、述部を最後に置くという点以外、修飾語の順序は自由です。しかし、この原則2は、そうはいっても「読んでいちばん自然な順序がある」との考えを本多氏は前提としています。修飾語の自然な語順とは「長い修飾語ほど前に置く」という考えです。先ほどの例文を、この自然な語順に並べ替えると、次のようになります。
「大雨の日ではあったが弟と一緒に彼女はプールへ行った」
この例では修飾語がすべて短いので、読点は削除しました。
この自然な語順が崩れている状態を本多氏は「逆順」と呼び、逆順の場合、読点を打つのです。
たとえば、書き手の意図によって、強調したい修飾語はVIP席として、最初の位置に持ってくることがあります。動作主である「彼女は」を強調したい場合、VIP席へ移動させます。ただし、逆順になるので、読点が必要になるのです。
【不自然】 「彼女は大雨の日ではあったが弟と一緒にプールへ行った」
【自 然】 「彼女は、大雨の日ではあったが弟と一緒にプールへ行った」
![]()
「誤解防止」とは、脳内関所が間違ったかたまりに区切って時間を浪費しないようにすることです。「文章の分かりやすさ」に対する私の基本的な考え方は、「文章解釈は、食品消化と同じ。事前分解してあれば、分かりやすい」というものです。したがって、一つのセンテンスを「事前分解」する読点は、センテンスを分かりやすくする有力な手段です。
「誤解防止に読点」の例を見てみましょう。
【違反例】 その蝶々はヒラヒラと舞いながら落ちてくる木の葉の中を飛んだ。
【改善例1】 その蝶々はヒラヒラと舞いながら、落ちてくる木の葉の中を飛んだ。
【改善例2】 その蝶々は、ヒラヒラと舞いながら落ちてくる木の葉の中を飛んだ。
【改善例1】ではヒラヒラと舞っているのは蝶々で、【改善例2】では木の葉です。
【違反例】その収入は本来資産に加算すべきである。
【改善例】その収入は本来、資産に加算すべきである。
違反例では、「本来」が「加算すべき」に係る副詞ではなく、あたかも「本来資産」という名詞句を作っているような誤解を与えます。
◎次回は 正確に意思を伝える技術 について。